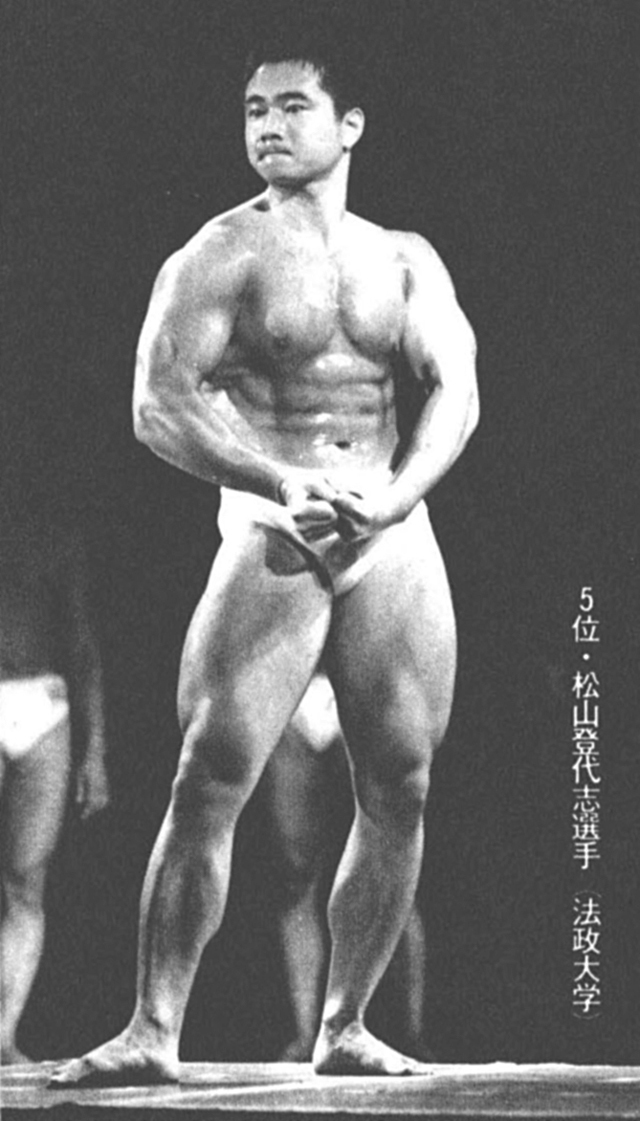前回のブログからずいぶん経過してしまった。というのは、1,2年時のトレーニング日誌を読み返していたからであり、記録を更新したり、回数を多くできたりした日をエクセル表に落とし込んでいく作業をしていたからである。日誌は今の自分が書く文字とは思えないほど小さくて細く、もちろん細いボールペンを使ったからだろうが、虫眼鏡を使わないと読めない文字も多々ある。
1年時のMAX記録は前回書いたように スクワット130キロ、ベンチプレス90キロ、デッドリフト170キロであった。2年時、1984年度の記録の変遷をエクセル表にしてみたので、見て欲しい。記録的に目立った成果があった日のみ掲載している。掲載の無い日は地道なトレーニングの日々であった。※MPはミリタリープレス、数字の並びはキロ、回数、セット数である。
| SQ | BP | DL | MP | 備考 | ||
| 1983 | 10月10日 | 115 | 85 | 180 | 法明定期戦 | |
| 11月10日 | 130 | |||||
| 11月16日 | 90 | |||||
| 1984 | 1月18日 | 70×10 | ||||
| 1月30日 | 110×5×3 | |||||
| 4月1日 | 90 | |||||
| 4月14日 | 185 | |||||
| 4月17日 | 90 | |||||
| 4月19日 | 132.5 | SQ100×10 | ||||
| 4月20日 | 92.5 | |||||
| 4月23日 | 135 | |||||
| 5月4日 | 92.5 | |||||
| 5月7日 | 90×2 | |||||
| 5月8日 | 90×3 | |||||
| 5月10日 | 140×2 | |||||
| 5月11日 | 95 | |||||
| 5月14日 | 100 | |||||
| 5月16日 | 100 | |||||
| 5月20日 | 135 | 97.5 | 185 | 関東パワー | ||
| 6月5日 | 130×5 | |||||
| 8月30日 | 90×3 | |||||
| 9月3日 | 100 | |||||
| 9月14日 | 95 | |||||
| 9月29日 | 110×5×5 | |||||
| 10月28日 | 新人戦 | |||||
| 12月11日 | 90×3 | |||||
| 1985 | 1月11日 | 62.5 | ||||
| 1月12日 | 65 | |||||
| 1月14日 | 102.5 | |||||
| 1月28日 | 90×4×2 | |||||
| 2月6日 | 130×3×3 | |||||
| 2月16日 | 135×3 | |||||
| 2月25日 | 90×6 | |||||
| 2月26日 | 150 | |||||
| 2月27日 | 70 | |||||
| 3月1日 | 140×3×3 |
2年生の5月14日にやっとベンチプレス100キロを達成したのだが、トレーニング開始から1年ちょっとかかっている。まあ、大した才能も素質も無いトレーニーだったと今さらながら思うのだが、当時は記録より効かせることをメインに考えていたので、素質云々は全く気にしていなかった。また、右肩の具合が思わしくなく、バーベルの安定感に欠けることが多く、持っている本来の筋力を出し切れていなかったように思う。
2月26日にスクワットを150キロ達成。この記録までに2年近くかかっている。フォームがなかなか安定せず、レグプレスで扱う重量からすれば脚の筋力はあるものの、スクワット姿勢になるとそれを活かしきれない症状があったと思う。この時はまだハイバースクワットであり、パワーリフティング大会のためにローバースクワットに取り掛かるのはずいぶん後になってからだ。
デッドリフトは185キロを5月20日に達成。関東学生大会での記録であり、公式記録となる。10キロのバーより20キロのバーの方が引きやすが、ファーストプルでバーがしなるので、そこで耐えないと両側のプレートが上がってこない感覚を覚えた。この時はまだフックグリップは採用せず、通常のオルタネイト・グリップだった。ただ、デッドリフトを週に1回でも練習に充てていれば、もう少し記録を伸ばすことができたと感じている。フォームもまだヨーロピアンスタイルで、妙なこだわりを持っていた。つまり、このフォームで200キロ引くまでは相撲スタイルのデッドはやらない、とか。今思うと、完全に間違ってます。はい。
ひとつ特筆したいのはミリタリープレスである。日誌を見るとバックプレスを行う日が1年時より多くなり、チーティングを採用することでオーバーロードの負荷がかかったことが功を奏したのか、2月27日に70キロをプレスしている。当時はこの重量でショルダープレスをする部員は自分ぐらいのもので、ひとりほくそ笑んでいた。ただ、合同練習期間中ではないので、誰も70をプレスするところを見ていなかったので、後から疑われたことについては腹立たしく思えた。
トレーニングのやり方を見てみると、ピラミッド法を当初採用していたのだが、徐々にセット法になり、多セットをこなすトレーニングに移行してきている。これは重量挙部の先輩の助言が大いに影響している。自力で挙げられる重量を潰れるまでやらないこと。潰れると筋力が低下する、という教えをしっかり守ってトレーニングしていくことになったが、当のボディビル部の先輩からは大した助言もなく、放置状態であった。